自由に選べるはずなのに、なぜか動けない──そんなあなたへ
「自由に生きなさい」「自分で決めなさい」
そう言われるたびに、心が少しだけ沈んでいく。
本当は、自分で選べることは喜ばしいはずなのに。
なぜか、選べない日が続くと、自分を責めてしまう。
「このままじゃダメだ」
「何かを始めなきゃ」
「ちゃんと、選ばなきゃいけない」
そう思いながら、動けない夜を何度も越えてきた人へ。
この記事は、「選べない時間」にも意味があるのでは?という視点から、
“選ぶこと”の美化にゆっくり問い直していきます。
焦らずに立ち止まりたいあなたへ、静かな道しるべとなりますように。
なぜ、選べないことに罪悪感を抱いてしまうのか?
「選ぶ=正しい」という現代社会の前提
現代社会は、こう言います。
「自分で決めることが大事」
「どんな人生を生きるかは、あなた次第」
「選択こそが、自由の証」
こうした価値観が浸透すればするほど、
「選べない自分」は、まるで“劣っている存在”のように感じられてしまいます。
「動けない自分=価値がない」と感じる構造
決められない。
動けない。
何かに踏み出せない──
そんな自分に対して、「私は何もできない人間なのかもしれない」と、
必要以上に厳しい目を向けてしまうことがあります。
でも本当に、そうなのでしょうか?
「選べない私」を否定しないための視点
迷っていた時間に宿る“誠実さ”
たとえば──
迷ってしまった日々。
誰にも言えなかった葛藤。
本当はやりたくなかったのに、笑って頷いた自分。
それらすべてを、「間違いだった」と言い切れるでしょうか?
むしろその中に、
“本音を無視しないまま、立ち止まった誠実さ”が宿っているかもしれません。
「まだ言葉にならない感覚」を信じて待つ
選べないということは、
「まだ本当の声が聞こえていない」状態でもあります。
そしてそれは、
“自分を信じて待つ”という、静かな強さでもあるのです。
そもそも、“選ぶ”ってそんなに偉いことなの?
選択は「能力」ではなく「プロセス」である
選ぶという行為は、何かに優劣をつけることではありません。
その時々の自分と対話しながら、何かに一歩ずつ向き合っていく。
それは、論理でも効率でもなく、“流れ”のようなものです。
だからこそ、「今は選べない」という状態もまた、
大切なプロセスの一部です。
選ばなかったことにも意味がある
人は、「何を選んだか」ばかりに注目します。
でも、「何を選ばなかったか」や「選べなかった時期」にも、
その人だけの物語が静かに刻まれています。
そこを無視したまま、「選ぶ力」だけを追いかけてしまうと、
かえって、自分自身から遠ざかってしまうかもしれません。
「正しく選ぶ」社会への違和感を言語化する
「何者にもなれない不安」に名前を与える
今の時代は、「何者かになれ」という空気が、あらゆる場面に漂っています。
でもそれは、言い換えれば「何者にもなれない自分は価値がない」という圧力です。
この空気にさらされ続けると、
“選べない自分”への不安や焦りが、どんどん強くなっていきます。
まずは、その正体に「名前を与える」こと。
そうすれば、少しだけ呼吸がしやすくなるはずです。
「選ばない」という選択を肯定する
「選ばない」
「決めない」
「そのままでいさせてほしい」
そんな選択があってもいい。
選ぶことだけが人生じゃない。
“留まる”ことにも、大きな意味がある──
そんな考え方を、いま改めて差し出したいのです。
まとめ:その迷いごと、生きていける力に変えていい
「選べないこと」は、決して弱さではありません。
それは、“自分の声を聞こうとしている証”です。
そして、まだ名前のない感情を抱きしめることも、
ひとつの誠実さです。
焦らなくていい。
急がなくていい。
「選べないまま、今ここにいる」あなたを、どうかそのまま肯定してあげてください。
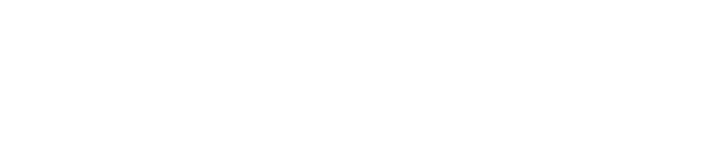
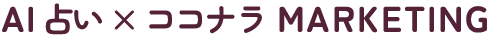
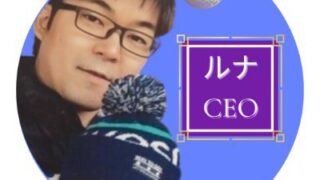
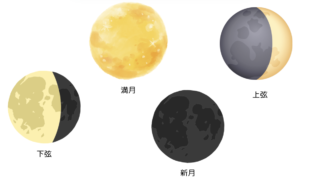



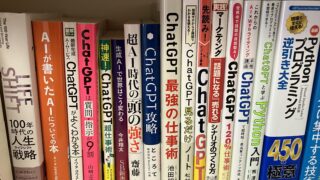





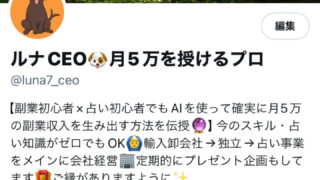



コメント