── 儀式化された癒しと、言葉にできない違和感
「自己肯定感を高めよう」のメッセージが、なぜか苦しい理由
「もっと自分を好きになろう」
「ありのままのあなたを認めて」
「自己肯定感を育てましょう」
──近年、SNSや書籍、セミナーでこのような言葉を見かける機会が増えました。
それは確かに、優しい響きを持っています。
自己否定ばかりだった人にとっては、救いにもなるメッセージかもしれません。
けれど私は、その言葉を見るたびに、どこかで小さく息が詰まるような感覚を覚えてしまいます。
それはなぜなのか。
どこに、何が引っかかっているのか。
それをずっと考えてきました。
“自己肯定”という言葉が、静かに「義務」になるとき
近年、自己肯定は「人生をよくするための鍵」のように語られています。
- 自己肯定感が高い人は成功する
- 恋愛もうまくいく
- メンタルが安定する
- 自分軸で生きられるようになる
こうした文脈での「自己肯定」は、いつの間にか“目標”になり、
さらに「到達すべき正しい状態」として機能し始めているように思えます。
そのとき、ふと気づくのです。
「自己肯定しなければいけない」
「自己肯定できない私は未熟だ」
──この“逆転現象”が、静かに起こっていることに。
肯定できない夜、許したくない自分も、ちゃんとそこにいる
「認めたくない私」へのまなざしを持つこと
誰にでも、こういう夜があります。
- 誰かの言葉にひどく傷ついた日
- 何もできなかった自分に呆れた夜
- 自己嫌悪でいっぱいになって、布団の中から出られなかった朝
そんなとき、「でも私は私を認めよう」
とは、どうしても思えない日もある。
だからこそ、私はこう考えたいのです。
「肯定できない私」も、確かに今ここにいる
その事実こそが、誠実さなのではないか?
「昇華」されてしまう感情たち
現代の癒し文化や自己啓発の多くは、
怒りや悲しみ、嫉妬や後悔といった“ネガティブな感情”を、
“どう乗り越えるか”に焦点を当てています。
もちろんそれも大切な視点です。
でも、それだけで語ることはできないはずです。
たとえば、
- 「私は怒っている」と正直に感じているとき
- 「私は今、誰も許せない」と思っているとき
そこに無理やり「でも私はOK」とラベリングしてしまうと、
感情は「感じきられる前に昇華されてしまう」ことになります。
昇華とは、ときに“美しく見える通路”です。
でも、その通路の途中で、
本当に大切だった声が、どこかに置き去りにされることもある。
「自己肯定できない自分」を肯定しない、という選択
肯定よりも大切な“残し方”がある
「肯定できない夜」に出会ったとき、
私たちは何をすべきなのか?
それは、無理にポジティブになろうとすることではなく、
そのままにしておく力──つまり、“感情の居場所”を保つことではないでしょうか。
肯定できない私は、そのままでいい。
認められない自分を、無理に美化しなくていい。
今は、まだわからないままでいてもいい。
この静かなまなざしを、自分自身に向けてあげられるなら、
それこそが、本当の意味での“自己理解”ではないでしょうか。
「癒し」が義務になったとき、何かが置いていかれる
ウェルネス文化に潜む“ポジティブ圧力”
現代社会のウェルネス文化には、
「整っていること」や「前向きであること」をよしとする空気が、
知らず知らずのうちに染みついています。
マインドフルネス、自己受容、セルフケア──
これらすべてが、素晴らしい概念である一方で、
それを“ちゃんとできていない自分”に対して、
「もっと頑張らなきゃ」というプレッシャーを生んでいる側面も否定できません。
本来、癒しとは「努力」ではなく「許可」のはず。
「今日は、肯定なんてできなくてもいい」
「この感情は、まだ名前をつけずにおいておこう」
そういった“余白の思想”を取り戻すことが、
ポジティブ疲れの社会において、とても重要なのではないでしょうか。
自己肯定感より大切なもの──「止まっていることを、許せる力」
変化を急がず、停滞と共にいる選択
成長、変容、アップデート。
現代は「変わり続けること」が称賛される時代です。
でも人には、変わらないでいること、
立ち止まりながら感じ続けることが、どうしても必要な時間もあります。
自己肯定感という言葉に急かされることなく、
ただ、その時間を味わいながら生きる。
そういう“静かな肯定”の形があってもいいはずです。
今日の問い:「“肯定できない私”を、そのままにしておくことは、本当にダメなことなのでしょうか?」
答えは、きっと一人ひとり違うはずです。
でも、ひとつだけ言えるとしたら──
「肯定できない夜」もまた、あなたの人生の一部であり、
そこで感じたことすべてに、意味があるということ。
そのままで、立ち止まっていてもいい。
その静かな選択にこそ、あなたらしさが宿っているのかもしれません。
そして、問いと共に、今日もまた一歩。
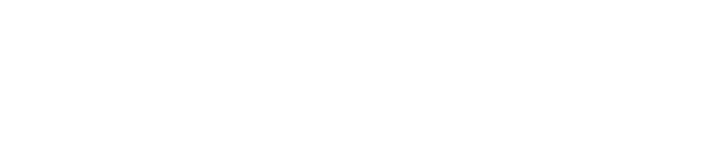
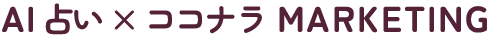
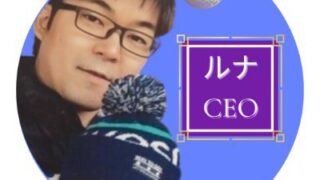
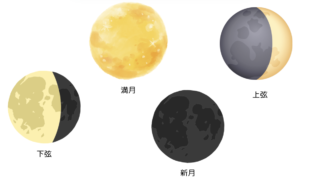



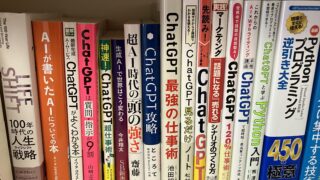





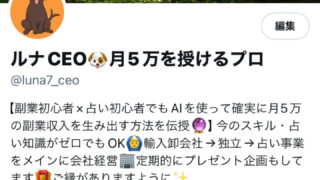



コメント